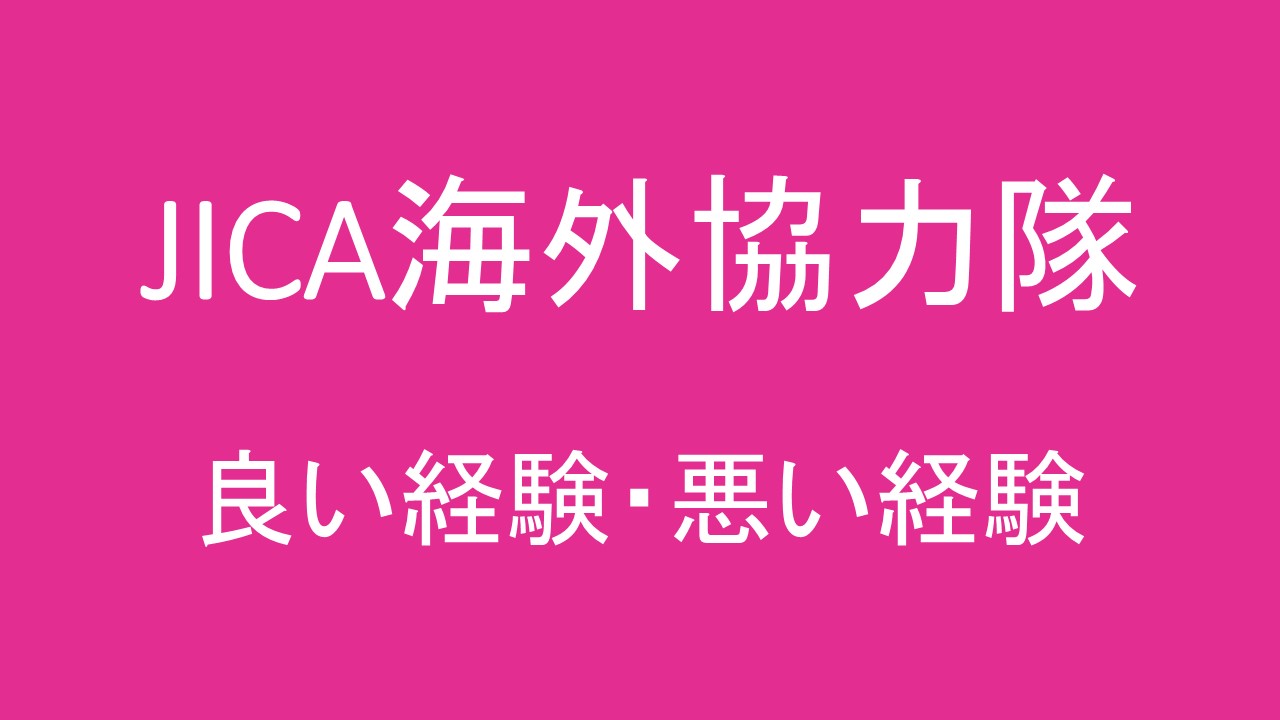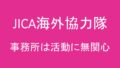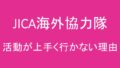・なにより嫌なのは「人のうざさ」
・アフリカに住んでいて良いことはほとんどない
私が選考に合格し退職した後に語学訓練が始まるまで派遣やアルバイトで生活費を稼いでいた。初対面の人と働く機会が多く、自己紹介でアフリカで二年働くことを伝えると「〇〇に2年も、大変ねえ。すごいね」とよく言われたものだ。当時はまだ任国に行ってもいないのに「すごいね」なんて言われても・・と冷めた対応をしていたが、実際に住んでみてその大変さが理解出来た。たくさんあるので良かった点、悪かった点をひたすら挙げていく。
良かった点
・途上国の実際を知れた
二年間の生活で治安の悪さ、インフラの悪さ、人々の貧しさ、差別、などテレビやYouTubeなどでは決して知れない実際の途上国を知ることが出来た。そして強く思ったのが「途上国は途上国のまま」ということ。これは別の記事で詳しく書くが、アフリカ諸国や人々は貧しい国にも関わらず先進国から支援を受けた物やお金を全く大事にしない。私は病院で働いたが、感覚的には日本だと10年は使えるものが任国だと2年ぐらいで壊れるような印象だ。空気が乾燥しており埃っぽい事、停電が1日に何回も起こるため物品管理においては日本より不利であることは間違いない。しかし人工呼吸器、モニター、電気メスなど先進国から寄付された高額な機材がとても雑に扱われていた。日本の病院では毎日カートなどに入っている薬の期限をチェックし小さな薬の一つの無駄すら無くそうとするが、派遣先の病院スタッフは全く無関心で物を無駄にすることが問題ないとすら思っているようだった。そういった場面をたくさん見て私は国際協力を進路に選ぶことを辞めた。全てが寄付で支給されている訳ではないが、一部ではあってもこういった物品に対して先進国からの寄付で賄われているのは事実だ。日本からの税金や寄付で支給されたものがこんなに雑に扱われるぐらいなら発展途上国への支援なんか一切やめれば良いとさえ思ったものだ。彼らが大事にするのは自分のスマートフォンとボロボロの車ぐらいだ。
・日本では決してできない経験が出来た
私が働いていた病院は産科や帝王切開が出来る大きな病院で、そういった産科や手術室でも活動していた。日本では女看護学生であっても出産は頭側から5mぐらい離れてしか見学できない。男子学生は母親が分娩室への立ち合いを拒否するケースがとても多く、男子学生は母性領域での実習にて会議室などで教科書を読み勉強することしかできない。しかしアフリカは男性の助産師がとても多い。日本ではそもそも男性が助産師になることが法律上できないが、アフリカでは男性が助産師になることが出来、男性の方が「力があって知識もある」と母親から頼られる傾向にある。これは私の印象ではなく、複数の女性助産師が話していた事である。こういった背景から私も分娩を近くで見学したり、帝王切開の手術に何度も立ち会う事が出来た。この産科やマタニティシアターのスタッフは特に優しく親切で、私に色々な事を教えてくれ今でも感謝の念でいっぱいだ。分娩期のアセスメントの仕方、アプガースコアの評価の実際など多くの事を学ぶことができ、日本から教科書を持ってくれば良かったとさえ思ったほどだ。「途上国の実際を知れた」ではアフリカの事をかなり批判したが、この産婦人科関連病棟では建物が新築されきれいな事もあり、物も大事に扱われていた。ここのスタッフを尊敬していることを強調しておく。
悪かった点
・インフラが整っておらず日常がストレス
私の任地は田舎だったこともありインフラが脆弱だった。泥交じりの水道水、頻回に起こる停電、ネット回線の遅さなど挙げればキリがない。停電が起こるとWi-Fiも止まるためスマホをいじるぐらいしかやることがなく、任国生活の2年で視力が若干落ちた。任国に来る前は自然に囲まれた生活でパソコンやスマホから少し離れた生活を送り、視力が少し良くなるのではと甘い妄想をしていたのが恥ずかしい。
・人がうざくてストレス
アフリカ人は日本人と比べると全く勤勉ではないし、誠実でもない。約束の時間に来ない、やると言っていたのやらない、借りたものを返さない、すぐにお金や物をくれと言う、などなど挙げればキリがない。職場に向かって歩くだけでバイクタクシーが何回も「チャンチョン」と声をかけてきて乗らないと纏わりついてくる。病院の看護師や医師は裕福なため良い人が多かったが、それ以外の人に何回「金がないから200円くれ」などとメッセージを受け取ったか分からない。任国の人の英語は現地語に影響されていたため、「ドアを開けてください」を「Close the door」と言う。お金を貸して欲しいという丁寧形にすべき文を「Give me money」などと言われたらあなたどう感じるだろうか?
土日に買い物に行けば小学生~高校生ぐらいの学生にニヤニヤしながら「チャンチョン」「チャイニーズ」と言われるため私は土日に外出すらしなかった。そういったくだらない奴らの相手をするのもどうかと思いながら、イライラしていた日は良くメンチを切って絡み返したものだ。「誰だ今俺の事をチャンチョンと呼んだ奴は」と睨みつけると何も言って来ないのもまた腹立たしかった。アジア系のことを「チャンチョン」と呼んでくる時点でそいつは低収入、教養なしといった要素が確定する。この表現が差別的な表現と知らず、もし本当の中国人だったらどう思われるかなんて教養のないアホ達は理解できない。教養のあるしっかりとした仕事についている人は絶対にそう呼んでこなかった。子供好きだった教員隊員ですら生徒からしつこく揶揄われるうちに「日本では子供好きと思っていたが任国に来て子供が嫌いになった」という人もいた。私もが街中にいる騒がしいだけの子供は大嫌いで全く相手にしなかった。
・派遣期間中の収入の喪失
任国に派遣されている最中は現地での生活費+日本に振り込まれるお金、支給される家賃を合計すると約15万だった。一年だと180万ほどだが、私が看護師として働いていた最終年度の年収は約500万円だったので手取り計算をしても日本で看護師をしていた時の半額になる。今後のキャリアで収入アップが出来ればアフリカ生活も悪くなかったと振り返りが出来るが、教師など現職参加で日本での勤務先から給料が出る場合以外は二年での収入減は避けられない。
・国際協力など結局うわべ面だけのものにすぎないことを痛感した
上述したようにアフリカの人々は基本的に物を大切にしないが、大切にしないのは「また支援で買ってもらえるから」「自分のものではないから」といった理由が主だ。物が大事に扱われない場面を見るだけでも嫌な気持ちになる。海外青年協力隊は技術移転を主な目的に派遣されているが、技術移転など夢のまた夢であり、多くの隊員が1労働力として扱われることに葛藤を感じながら活動することになる。また隊員がひどい扱いを受けたケースもあり例を可能な限り挙げてみる。
例1:学校教員。職員会議の時間が長くなり、授業時間を削ってまで不毛な内容を議論するため隊員が「会議の時間は生徒が帰った後でも取れる」と授業後の会議を提案するが現地の職員は結局無視してだらだらと会議を継続。授業時間を削る習慣を辞めなかった。
例2:学校教員。職員室にいる現地人教員達がティックトックやYouTubeばかりを見てまともに仕事をしていなかった。職員室にいても仕方ないと生徒に補習をしたりスポーツを教えたりして生徒と関わるようにしていた。すると現地人教員から「あいつは仕事に来ていない」とJICA職員との話し合いの際に一方的に批判される。現地人教師が授業時間外にろくに職員室から出ていないのが原因だが悪びれる様子もなかった。現地の教員にとっては居室やグラウンドで生徒と関わるより、職員室でスマホをいじる方が仕事をしていると捉えているのだ。
例3:学校教員。赴任当初から「何か食べるものは持ってきていないのか」「日本からのお土産はないのか」と繰り返し尋ねられるため「そもそもボランティアとして来ている、お菓子を持ってくるために来たんじゃない」ときっぱり言うと一部の職員が隊員に対して挨拶をしないなど無視をするように。
例4:看護師隊員。病院での掲示物を作成するために上司に事前相談をした上で、費用(数千円ほど)を後払いで貰う約束で物品の費用を立て替えで払う。後日上司に請求するもずっとはぐらかされ、結局支払われず。複数人に聞きとると隊員に支払われるべき活動費を自分の懐に入れていたことが判明。
例5:看護師隊員。病院でのチーム活動に加わり活発化したり指導してほしいと要請を受け病院に赴任するとチームそのものがなかった。上司に掛け合うも1年以上チームが出来ず、結局個人で活動するはめに。
例6:日本語教師。赴任後に所属長に挨拶をするために秘書経由でアポを取り挨拶に向かうも直前でドタキャンされ、そのケースが何度も続きなかなか挨拶できないでいると所属長が「日本人は挨拶にも来ないのか」と言っていることを知った。
例7:日本語教師。大学にて日本語教育のレベル向上が要請内容だったが、大学では現地の法律上隊員が授業を直接出来ず、教員に指導することになったが現地教員が「自分の授業を見てほしくない」と授業見学すらできず。プライドが高いことが原因だが、テストの作成や丸付けなどの雑用はやらされ繁忙期には8-22時の勤務を強いられることも。
など例を挙げればキリがない。多くの隊員が「自分が2年働いても何も残らないのではないか」という失望の念を抱きながら働き、任国を去ることになる。途上国で働いた隊員は多くの場合その経験をキャリアやスキルアップの糧とすることが可能だが、途上国には何も残らない。私の私見だが「日本という先進国から来た隊員がキャリアアップ(収入アップや社会的地位の向上)する一方、途上国は途上国のまま」という事実がある。日本はJICAでの活動実績を国際的にアピールでき、隊員もステップアップ出来るが途上国は置き去りだ。JICAや隊員が任国やアフリカ人を置き去りにしているのではなく、怠惰なアフリカ人たちがレベルアップする機会を自ら放棄している。この文は強調しておく。勝者は勝者、負け犬は負け犬のままということだ。この私の意見に批判的な方が多くいることを覚悟してこの記事を書いているが、私は自信の経験から「国際協力」や「フェアトレード」などという言葉が嫌いになった。協力隊事業の実態は他記事を参考頂きたいのだが、例えばフェアトレードを謳っている商品としてコーヒーがある。フェアトレードを謳っている商品を買う事はなんだか善い事をしているような気になるが、途上国で実際にコーヒー栽培に従事している末端作業員までお金が行き届いているかを知る由はない。多くの場合は作業員を雇用している大企業の利益になる事は想像に難くないことだ。実際、私の任国では元隊員が起業し現地人と共同して農家の収入向上を~などと謳い、ネットで調べると名前が出てくるほどだったが実際は日本や現地からのインターン生にロクに金を払わずに商品開発や店舗運営をさせていたそうだ。
長々と書いてしまったが、結論としては協力隊員として途上国で働くことは多くの場合ストレスフルだ。私は「隊員として働きたい」という人を見かけたらこれからは極力止めるつもりだが、もし応募を考えている人はこの記事を読んでもう一度考えなおすことをおススメする。